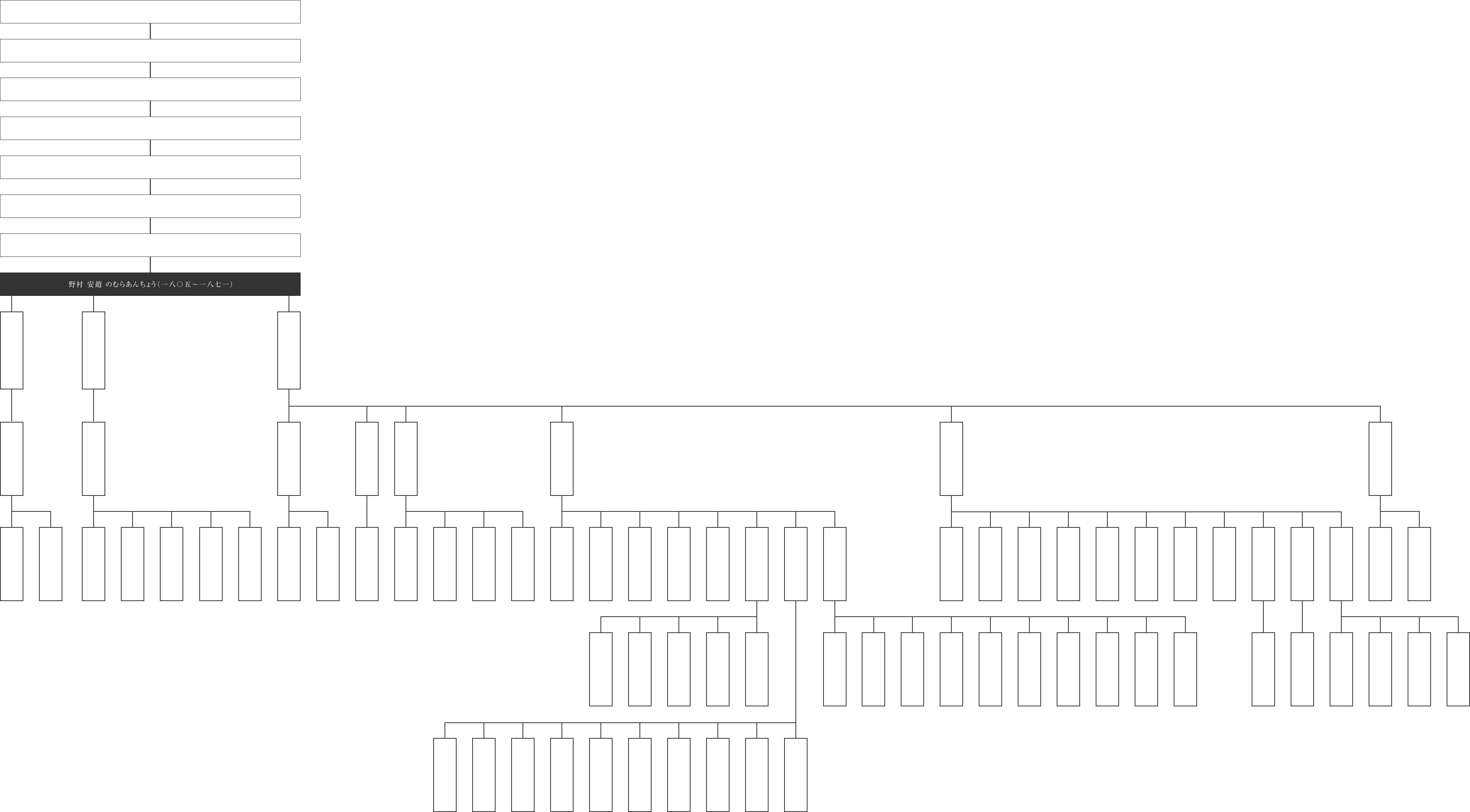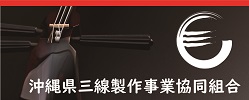琉球古典音楽野村流保存会とは
- TOP
- 琉球古典音楽野村流保存会とは
野村流保存会の名称由来
琉球古典音楽野村流保存会(以下本会)の名前の由来は、
琉球王朝時代にさかのぼる楽譜「工工四」(くんくんしー)
を高弟らと共に今日、広く普及している教則本の形に細密化
した俊才、野村安趙 (のむら あんちょう、一八〇五~一八
七一年)を祖とするところに返ります。安趙らが改良した工
工四は時の王に採用されたため「欽定工工四」「御拝領工工
四」とも呼ばれ、本会はこのような歴史と伝統ある音楽を後
世に正しく保存・継承すべく一九五五(昭和三十)年に野村
流古典音楽保存会の名称で初代会長、屋嘉宗勝のもと、三線
百十名と箏曲三十名の会員で発足しました。
その後、会員らが結束しながら研鑽を積み、「和衷の精神」
を礎とする会運営に従い県内外に仲間を作り、現在は笛・胡
弓部門を含め会員数千名を超える団体となりました。
県民の共有財産である
古典音楽・三線
そして今、古典音楽は人の心に貴(とうと)さと安らぎをも
たらすものだという、会創立に関わった先達たちの強い確信と
想いは、多くの師匠らに受け継がれながら様々な試練の時代-
ときもウチナーンチュ(沖縄県民)の暮らしと心に寄り添い、
慰めと憩いを与え、新しい時代においてなお新たな担い手によ
り技量他さらに研ぎ澄まされようとしています。
本会はこれからもこの島の先人が生み、守り残してきた沖縄
の宝、県民の共有財産である古典音楽のさらなる継承と発展を
通じ、青少年の健全育成をはじめ、すべての人々の心の安寧の
ために会員一丸となって力を尽くしてまいる所存です。
~ 本会の目的・会員心得 ~
琉球古典音楽野村流の
保存・継承・沖縄の音楽文化の向上・会員の親睦

主な沿革
- 2016年(平成28年)
- 5月
- 中部支部を中部北支部と中部南支部に発展分割
- 2014年(平成26年)
- 1月
- 会名を琉球古典音楽野村流保存会に改称
- 2011年(平成23年)
- 5月
- 九州支部結成
- 2008年(平成20年)
- 2月
- 宮古島支部結成
- 1994年(平成6年)
- 12月
- 早弾楽譜作成委員会発足
- 1992年(平成4年)
- 8月
- 三箏会発足
- 1987年(昭和62年)
- 1月
- 組踊地謡研修部会発足
- 1983年(昭和58年)
- 5月
- 宮古支部創立総会
- 1982年(昭和57年)
-
12月
5月 -
南部支部創立並びに公演
那覇支部創立総会
- 1981年(昭和56年)
- 10月
- 北部支部結成
- 1979年(昭和54年)
- 6月
- 第1回師範・教師研修会
- 1978年(昭和53年)
- 3月
- 関東支部結成
- 1975年(昭和50年)
- 4月
- 久米島支部結成
- 1973年(昭和48年)
- 4月
- 関西支部結成
- 1964年(昭和39年)
- 7月
- 伊江支部結成
- 1961年(昭和36年)
- 2月
- 八重山支部結成
- 1958年(昭和33年)
- 5月
- 中部支部結成
- 1957年(昭和32年)
- 1月
- 箏曲保存会の独立
- 1956年(昭和31年)
- 10月
- 赤犬子(アカインク)の記念碑建立
- 1955年(昭和30年)
-
12月
6月 -
工工四全巻発行する
野村流古典音楽保存会結成会(12日)
歴代琉球音楽研究家系譜